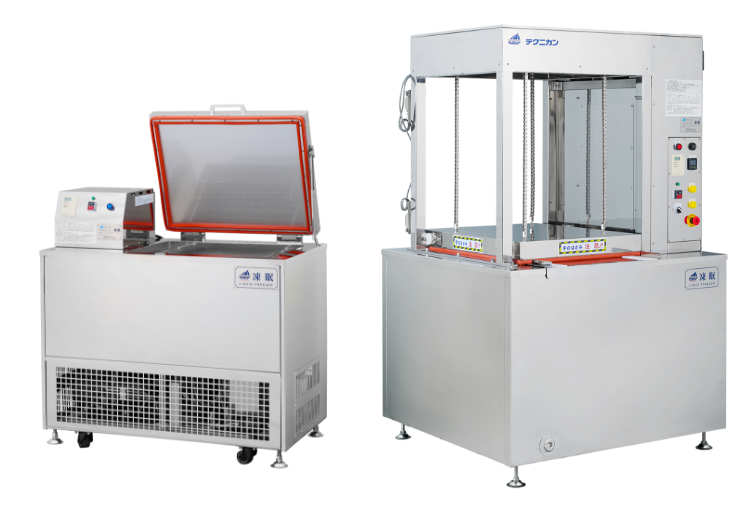「復興常備食」を凍眠で急速冷凍 | 災害復興の現場で活躍する凍眠の冷凍食品

今回は徳島県阿南市で「復興常備食」を手がける株式会社一生の北條社長にお話をお伺いしました。もともと「いちご農家」さんとしてLM-45をご導入いただきましたが、今回は「復興常備食」にフォーカスを当てて取材を進めていきます。
復興常備食とは?
-
「非常食」とは似て非なるもの
食材として備蓄しておくだけでなく、日常使いもしやすいことを念頭に作られています。「復興常備食」ができた背景として、北條社長がソーシャルワーカーとして日赤に従事していた際、東日本大震災の復興支援のため被災地を訪問。その際に小麦アレルギーを持つ子どもがやむを得ず支給された非常食を食べなければならない状況を目の当たりにし、「災害時の食の選択肢の少なさ」を解消すべく、復興常備食事業を立ち上げたとのことです。
目次
凍眠×復興常備食

凍眠だからこそ叶う理想像
復興常備食を「普段から食べ続けられる美味しい冷凍食品」と語る北條社長。復興支援の経験から、「非常食を食べ続けると飽きてしまう」「非常食は日常使いしづらい」という課題を感じ、「出来立てのおいしさ」「オーガニックのクオリティ」をそのまま備蓄するための手段を模索した結果、凍眠にたどり着いたとのことです。
ただし、非常食が悪いわけではありません。北條社長曰く、あくまでも非常食との両輪との事。非常食は携行性や利便性に優れているため、復興支援の現場では必需品。美味しさや健康へのアプローチを考えた際、復興常備食が被災者の方々に癒しの食事機会を提供できる、としておられます。
そこで、復興常備食は美味しさへの妥協をせず、保存料も使用せずに長期保管をする。日常使いしやすい冷凍食品を全国各地で備えておき、被災地にはキッチンカーで届けるスキーム。これらの条件下において、個パック化され、かつ自然解凍で美味しく食べられるのは理想的とのことです。
復興現場での凍眠冷凍食品の有用性

北條社長曰く、震災直後から復興のあらゆるフェーズにおいて、復興常備食は活躍するとのこと。一般的に、災害時は電気を含むインフラが被災することで、電源確保が難しくなるため、有事の際、冷凍食品は備蓄に適さないと考えられます。そのようなディスアドバンテージがあるなか、北條社長の描く復興常備食の在り方はどのようなものなのでしょうか。
発災直後も「自然解凍で美味しく」
「発災直後に電源が落ちた場合、凍眠の冷凍食品なら自然解凍で美味しく食べることができる」と語る北條社長。自宅保管だけでなく、避難所にも分散備蓄として凍眠の「復興常備食」を設置しておくことで、自宅でも避難所でも食料確保につながるとのこと。
周辺地域で備蓄しておくことで「即応性」が高い
能登の震災復興に赴いた際にも徳島に備蓄していた復興常備食をキッチンカーを用いて配給したとの事。出動要請があってから数時間後には徳島から能登に行き、食料の配給ができたことから、「即応性」の高いスキームであることが証明されました。
真空パックしているから衛生的
凍眠冷凍するということは、真空パックなどを活用することが前提となるため、製造後から開封されるまでの間に異物やウィルスの混入リスクが大幅に低減されます。そのため、食品ルートでの感染症予防にも繋がる、との事。
提供時に皿や容器が不要
自然解凍や湯せん解凍をした後、パックの中の食材をそのままお箸やスプーンなどで食べることができます。また、おにぎり、お箸すら不要な食品もあるため、いろいろな意味で食べやすいパッケージです。
被災地での配給力が高い
キッチンカーであれば冷蔵庫、冷凍も備わっていますが、即応性をより高めるために解凍しながら運ぶこともできます。また、冷凍状態で現地まで輸送し、その後、冷凍食品として被災者に配布することも可能。北條社長曰く、「キッチンカーの炊き出しの場合、6時間で500食程度である中、冷凍で復興常備食を配布した際、1時間で1,500食も支給することができた」との事。自然解凍でも食べられる凍眠の復興常備食ならではの機動力です。
「復興常備食」スキームの概要と展望
政府、キッチンカー経営審議会との連携
民間企業である以上、キャッシュフローがなければ社会的意義があったとしても長期的に見て安定してサービスを提供できません。やはり、実体経済の中での消費サイクルや行政機関との連携は不可欠です。北條社長曰く、能登半島の復興支援においては政府との連携があったとの事。
能登復興支援時のスキーム
発災後、政府から日本キッチンカー経営審議会に要請があり、その審議会からさらに徳島県キッチンカー協会に出動依頼、という枠組み。北條社長は徳島県キッチンカー協会の理事を務めていることもあり、自ら運転し、支援に赴いたとのこと。
今後の展望
全国の自治体が復興常備食として冷凍で備蓄し、被災地の周辺地域からキッチンカーで駆けつけるというモデルを掲げている北條社長。民間企業である以上、「消費サイクル」を意識し、「日常使いしやすい」というコンセプトも大切にされています。加えて「消費」だけでなく「生産」においても農家さんなどの生産者に資するような枠組みづくりをすることで、減災につながる社会構造と経済活動の両立を目指されています。